
新たな情報収集方法『AI検索』活用が拡がる理由と各社のサービス特徴とは
AIを利用した検索サービスは、私たちの身近なところで活用が進み、ビジネス・教育・プライベートなど多くの分野で利用されるようになってきました。AI検索の登場によって、人々の情報検索の仕方にも変化が表れはじめています。
今回は、AI検索の特徴や活用方法についてご紹介いたします。
1.AI検索とは?
AI検索とは、AIがユーザーの検索意図や文脈を理解することで、高度な検索機能を提供する検索サービスのことです。従来の検索エンジンでは、キーワードの入力から導き出される回答がアルゴリズムによって表示されていましたが、AI検索では、自然言語処理によって、複雑な質問に対しても文脈に沿った情報を抽出・生成することができます。また、会話形式で質問できるため、求めている回答に対して追加の質問を重ねることで、より的確な情報を得やすくなります。
AI検索の特徴は、その情報処理能力にあります。プロンプト(特定のタスクや質問に答えるための指示や質問を含むテキスト)に入力した質問に対して、AIがWeb上の膨大なデータを瞬時に検索し、要約した形で情報を提示します。従来のWeb検索では検索結果からユーザーが一つ一つ情報を見に行き、精査していたことに比べると、まとまった情報を瞬時に得ることが可能となります。これらの特徴からも、AI検索エンジンの活用が時間の短縮や効率化につながると考えられます。
2.AI検索活用の動向
メディア環境研究所が2025年1月から実施した「検索サービス利用実態意識調査」によると、情報を検索する場面では依然として検索エンジンが一般的であり、現在でも年齢を問わず、9割以上の人が利用するなど圧倒的な利用率となっています。ここに加えて、YouTubeなどの動画検索や、SNS検索、AI検索といった検索ツールの利用の割合が高まってきています。年齢別の比較では、若年層ほどSNS検索やAI検索の利用が高く、10~20代のSNS検索は77.3%、AI検索は47.4%、検索エンジンは94.4%と多様な検索ツールを利用しているという結果がでています。
AI検索の魅力として、専門的な情報がわかることや、文章で質問ができる点が挙げられており、若年層ほどAIが要約する情報への満足度が高く、検索の省力化が進んでいることも見えてきました。タイパを求める現代の若年層ならではの傾向かもしれません。年齢層による違いもありますが、検索内容によっても、ツールの使い分けが進んでいるようです。
AI検索は、ビジネス分野での膨大な資料からのデータ検索や、顧客からの複雑な問い合わせの対応などにも活用され始めています。業務の効率化やコストの削減、意思決定の迅速化にもつながっており、今後もさらに活用の場面が増えていくと考えられます。
引用元:
株式会社博報堂 メディア環境研究所:「検索サービス利用実態意識調査」

3.主要なAI検索エンジン
AI検索には、「検索特化型」と「ディープリサーチ型」があり、それぞれ検索目的やアウトプットが異なります。検索特化型は、既存のWebから迅速に回答を選び出し、短い要約や箇条書きで提示します。スピードと網羅性を重視する場合に適しています。一方、ディープリサーチ型は、複数の情報源から得た情報をもとに、AIが自律的に分析・推論・洞察の生成を行い、レポートにまとめます。大量のデータを処理するため、回答までに数分から30分ほど時間はかかりますが、市場調査や競合分析、ビジネス戦略の立案などのより専門的な情報を提示することができます。大規模言語モデル(LLM)ベースのDeep Research機能があるものや、学術・医療・金融など特定の専門分野に特化したAI検索ツールも登場しています。
3-1.検索特化型AI
ここからは、検索特化型AIの具体的なサービスについていくつかご紹介します。ツールは様々ありますが、現状、基本的な機能に大きな違いはないようです。自分に合った使いやすいツールを選ぶと良いでしょう。
-
OpenAI社が提供するChatGPT Searchは、対話形式で最新の情報を得られる点が特徴です。ChatGPTは学習データベースからの生成であるのに対し、ChatGPT SearchはWeb上の検索結果の要約から回答を導きだします。そのため、リアルタイムデータの収集が可能となります。
プロンプト入力画面はChatGPTとChatGPT Searchともに同じですが、ChatGPT Searchを利用する際には、地球儀マークの「検索」をクリックしてから質問を入力します。特徴
・Web検索も選択可能
・音声対応
・ソースにアクセスできる
・最新の情報を網羅している
・グラフや図表など視覚的表現で見やすい利用シーン
・ニュースや株価などリアルタイムデータの収集
・話題のトピックやトレンドの調査
・視覚的な情報の整理金額 無料
-
Google社が提供するGeminiは、Google検索との連携により広範囲のソースを検索することができます。Google Docs、Gmail、Googleマップ、YouTubeなどとも連携しており、文章作成や文章の要約、情報提供によりユーザーをサポートします。また、マルチモーダルAIであるため、テキスト、画像、音声、動画など異なるデータ形式を利用できます。
特徴
・マルチモーダルに対応
・Google検索との連携で最新情報を提供
・長文の処理や理解ができる利用シーン
・動画や画像の生成
・長い文章記事や論文の要約
・リアルタイムの翻訳金額 無料
-
Microsoft Copilotは、Microsoft 365アプリ(Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teamsなど)と連携しています。そのため、生成したデータの修正・共有などがスムーズに行えることが特徴です。また、音声や視覚機能からの情報入力にも対応しているため、音声によってプロンプトを作成することができたり、カメラや共有画面で写した情報を解析することができます。この機能を使うことで、目の前の物体やパッケージの情報の解析にとどまらず、Web画面の要約や外国語をリアルタイムで翻訳することも可能です。
特徴
・Microsoft 365アプリと連携
・図や絵文字による見やすいアウトプット
・Vision機能で視覚的な情報を解析
・翻訳機能
・音声対応利用シーン
・企画やアイデアのブレインストーミング
・メールの下書きを生成、送付
・手書きメモをVision機能で読み取りデジタル化金額 無料
- Perplexity(Perplexity社)
Perplexityは、複数のAIモデル(GPT-4、Claudeなど)を使用しているため、幅広い情報源から最新の情報を得ることができます。また、明示されたソースの中から不要なソースを外して出力しなおすこともできるため、必要な情報に限定しやすい仕組みとなっています。特徴的な機能としては、プロンプトに対する回答と併せて関連する質問が提示されるため、深い理解につながりやすくなっています。ファイルアップロード機能を使えば、PDFの自動要約やWeb検索と組み合わせた情報の収集が可能です。
特徴
・リアルタイム情報の検索
・情報源を絞った検索が可能
・プロンプトから想定される次の質問を提示
・ファイルアップロード機能
・AIモデルの選択が可能(Perplexity Proのみ)利用シーン
・最新ニュースの調査や市場動向など情報収集
・レポートやプレゼン資料作成
・アップロードしたファイルの要約や翻訳
・比較表や図表の作成金額 無料
Perplexity Pro 月額20ドル - Genspark(MainFunc社)
Gensparkは、収集した情報を俯瞰的に、わかりやすく提示する機能が備わっています。マインドマップや動画で回答が可視化されるため、全体像を把握したい際にも有効活用できます。また、「Sparkpage」では検索した結果が自動的に生成され、編集や共有することができます。
特徴
・検索結果をマインドマップや画像、動画などで可視化
・情報を俯瞰して把握できる
・「Sparkpage」で検索結果を要約して提示
・ファクトチェック機能利用シーン
・市場調査と資料作成
・「Sparkpage」で作成した情報の共有
・ファクトチェックエージェントによる専門的な検証金額 無料
- Felo(Felo株式会社)
Feloは、日本のスタートアップ企業が開発しています。そのため、日本語での検索能力に優れており、的確な日本語の回答を生成することができます。さらに、検索結果をもとに資料を作成することができたり、図解・可視化機能では、テキストを可視化し見やすい図解として生成、修正できるなど、ビジネスで活用しやすい機能も備えています。
また、フォーカス機能を使うと、検索源をWeb検索、チャット、SNS、論文、ドキュメント、Xに限定して検索することができるため、必要な情報を絞りやすくなります。
特徴
・多様な情報源(SNS、学術論文、ドキュメントなど)からの検索が可能
・情報源を指定するフォーカス機能
・マインドマップ、プレゼンテーション作成機能
・多言語対応
・要約機能(Webページ、YouTube)利用シーン
・検索結果から自動で資料を作成
・テキストから図解資料の作成金額 無料
引用元:
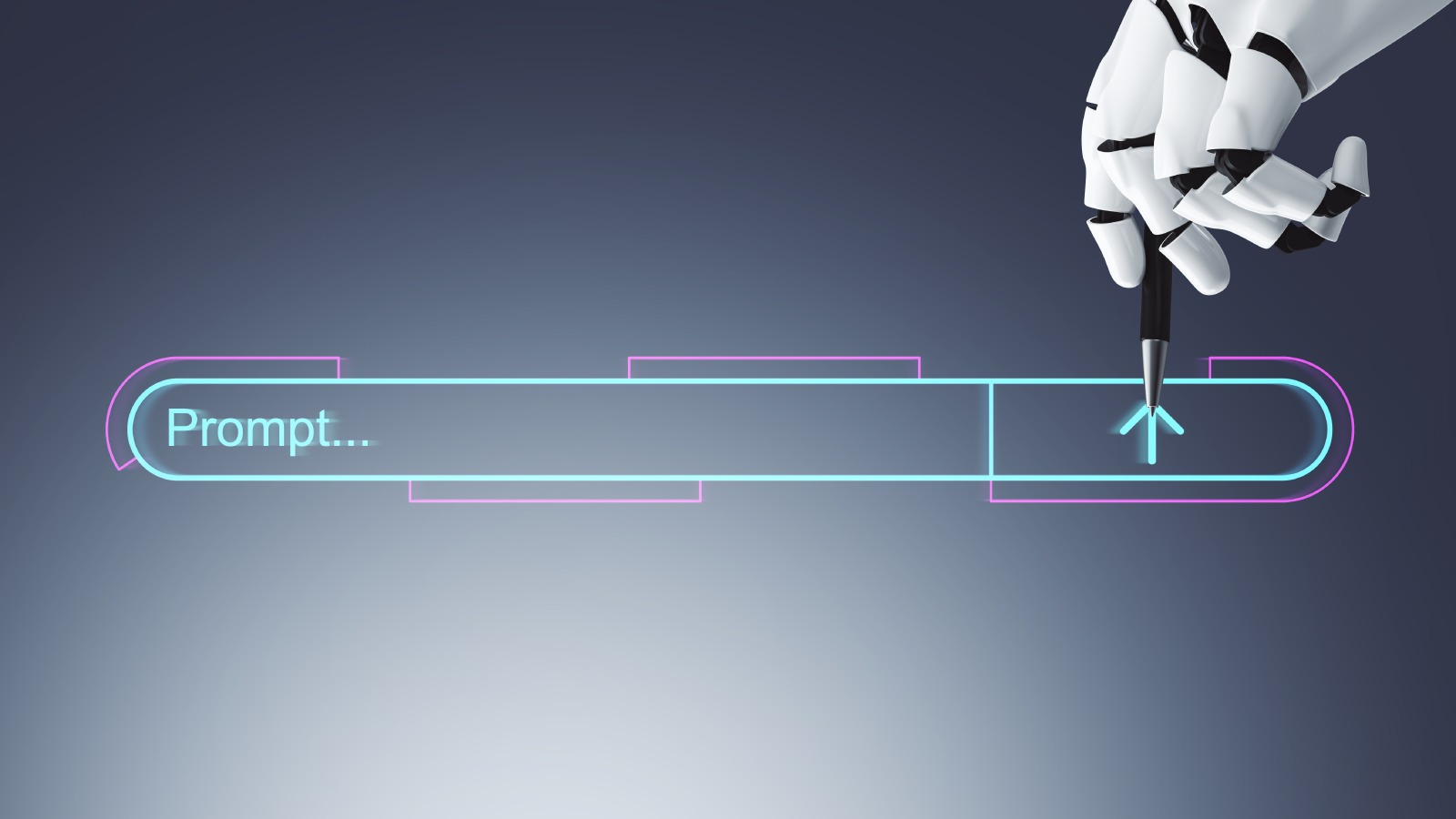
3-2.ディープリサーチ型AI
さらに複雑な情報の収集・分析・レポートにはディープリサーチ型が適しています。プロンプトに対して膨大なオンラインリソースから情報をまとめるため、ユーザーは情報をまとめる時間を大幅に省力化することが可能となります。多くの検索AIサービスは、ディープリサーチ機能も搭載しており、簡単に使い分けることができます。プランによっては回数の利用制限が設けられるなどの条件があります。
- ChatGPT Deep Research(OpenAI社)
ChatGPT Deep Researchでは、ChatGPTよりも深く広い範囲からのリサーチが可能であるため、学術、法務、技術や業界の動向などの分析に適しています。チャット入力欄の「詳細なリサーチ」をクリックすることで、ディープリサーチ機能の利用が開始します。利用プランによってユーザー検索件数に制限があります。
特徴
・複数の最新情報を同時に比較
・常に出典付きで提示
・検索結果に対して「もっと詳しく」で深堀りが可能
・解釈や推論も含めた思考型の回答利用シーン
・最新の時事問題の調査と複数データの比較
・業界やビジネス動向の分析
・科学・医療・法務など論文の調査金額と検索件数
・無料(5件/月)
・Plus 月額20ドル(25件/月)
・Pro 月額200ドル(250件/月)
- Gemini Deep Research(Google社)
Gemini Deep Researchは、複雑な情報調査やレポート作成などの特定の目的に特化したAIで、自律的に複数の工程を実行するエージェント的なシステムが組み込まれています。チャット入力欄の「Deep Research」をクリックすることで利用が可能となります。
特徴
・広範囲のデータ収集と分析
・大量の情報処理ができ、複雑なテーマも扱える
・最新の情報へのアクセスが可能
・複数情報から情報の正確性と質を判断
・Googleツールとのスムーズな連携が可能
・多言語に対応利用シーン
・市場トレンド、課題の把握などの市場調査
・業界の最新動向の予測
・事業戦略策定のための情報収集
・顧客インサイトの把握
・学術研究、教育分野でのデータ収集と文献提示金額と検索件数
・無料(5件/月)
・個人用:Google One AI プレミアムプラン 月額2,900円
・法人用:Gemini Business 月額2,260円
※掲載のプランは料金は執筆時点のもので、今後変更となる可能性があります。
引用元:
Google合同会社:Gemini Deep Research
AI活用に関するご相談はこちらから
4.検索のコツ
検索型AIでは、プロンプトによって出てくる回答に差がでるため、プロンプトの書き方は非常に重要となります。そのため、「何を」「どのように」「なぜ」を具体的に指示することがポイントとなります。プロンプト設定のコツをつかめば、的確な回答につながり、AI検索をうまく活用することにつながります。

4-1.プロンプト作成のポイント
AIはプロンプトの内容に基づき、情報の検索・収集・生成を行います。そのため、AIが情報を出力しやすいようなプロンプトが求められます。
- 目的や意図を伝える
調べる目的や求める結果を「何をしてほしいか」「どんな結果を求めているか」といった形で示すことで、AIがより的確な答えを出しやすくなります。
- 具体的な指示を出す
プロンプトに具体的な対象、条件、形式をいれることで、求める回答に近づけることができます。例えば、「気温の変化」と指示を出すより「2020年以降の東京の気温上昇の影響について政府機関の記事を中心にまとめて」といった、年号や場所、目的を具体的に示すことでより的確な情報を得やすくなります。論文、ニュース、政府機関などの必要とする情報源からの収集を指定することもできます。
- 回答の形式を指定する
回答の形式の条件をあらかじめ伝えることで、わかりやすい形式で出力を得ることができます。「箇条書き」「表形式」「時系列」「〇〇字以内の要約」「〇〇向けのレベルで」などの条件を加えることで詳細な情報に近づけます。
4-2.求める回答が得られない時の対処法
前述した内容のプロンプトを入力しても、得られる回答に満足いくものでない場合には、条件を変更するなどの方法を試みます。
- プロンプトを見直す
改めてプロンプトを見直し、具体的な指示内容を追加します。指定した条件が抽象的すぎるとあいまいな条件となりやすいため、例を示すなどして詳細な指示を加えます。
- 再検索、再質問をする
回答が意図とずれている場合などは、再度質問をすることで精度の高い回答に導きます。AI検索サービスによっては、回答結果と併せて関連する質問が提示される場合もあり、これらを利用することで情報を深堀りすることができます。
5.まとめ
ここまで、AI検索の特徴と使い方についてご紹介しました。各社AI検索サービスは、特徴やUI/UXがやや異なるため、実際に使用してみることで用途や使い勝手の良いサービスを見つけることができるでしょう。なお、AI検索は、使用の仕方によっては情報漏えいにつながる危険性もあるため、個人情報やプライバシーに関する内容、会社の内部情報等の検索や入力は控えるか、会社の規定に基づいた利用をする必要があることを十分に理解しておきましょう。
クロス・コミュニケーションでは、企業が抱える課題や目的を理解し、AIをビジネスに活用するためのご相談も承っております。その後の戦略立案、システム開発・実装、運用及び改善までの支援もサポートいたします。是非、お気軽にお問い合わせください。







